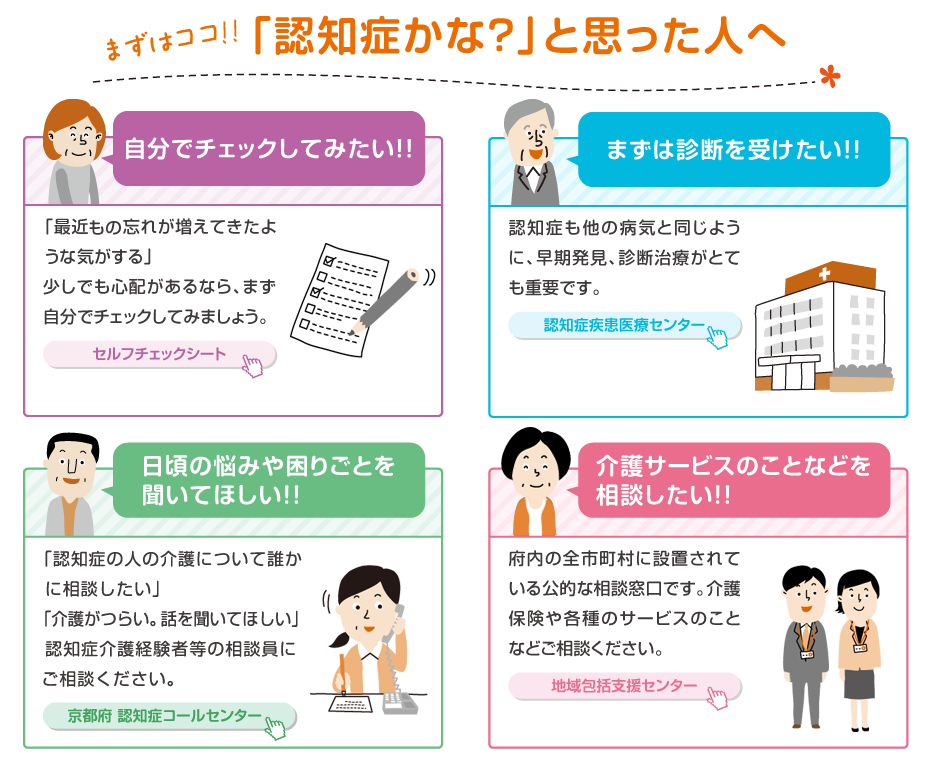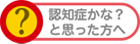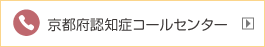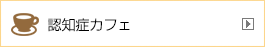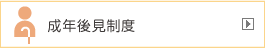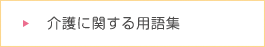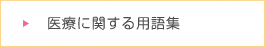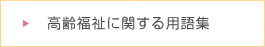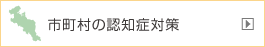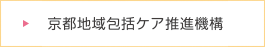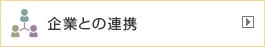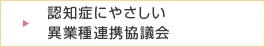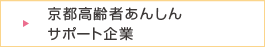利用できる制度
若年性認知症の人と家族の相談に適切に対応し、必要な支援をするための概要を示します。若年性認知症の特質を理解した上で、各段階で利用できる制度等をうまく使いながら、医療や介護を含む多職種が連携して支援をすすめることが大切です。
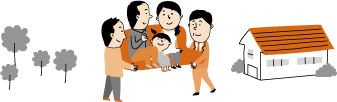
休職や退職をする頃
休職や退職をすることになれば、経済的な問題が、生活や子どもの教育などにも直接影響します。休職・退職後の日常生活をどう生きるかという支援とともに、経済的に本人・家族を支えるサポートが求められます。
【詳細はこちら】
◦傷病手当金
◦雇用保険(失業給付)
◦自立支援医療(精神通院医療)
◦精神障害者保健福祉手帳
働いたり社会参加をしたい時
仕事を辞めても、早期段階に対応したサービスが少なく、行き場がなくなってしまう可能性もあります。就労や社会参加の要望があれば、さまざまな可能性を追求して、本人の状況に応じて支援を行っていくことが必要です。
【詳細はこちら】
◦障害者の就労支援
◦今後の活用が望まれる制度やサービス(認知症初期対応型カフェなど)
◦利用できる事業所
◦精神科デイケア
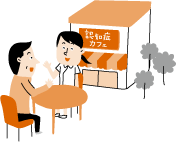
症状や状態に応じて
ケアマネジャーなどが若年性認知症の人を支援する場合、どうしても介護保険のサービスに視点が偏りがちですが、症状や状態に応じて障害福祉サービスなど多様な制度を活用する必要があります。
【詳細はこちら】
◦介護保険制度にもとづく介護サービス
◦障害者総合支援法にもとづく障害福祉サービス
家計の支援
税の減免や費用の軽減、各種の手当や利用可能な貸付など、家計を支援する諸制度は、必要な人にタイムリーに情報を提供することが重要です。
【詳細はこちら】
◦障害年金
◦特別障害者手当
◦障害者控除
◦医療費控除
◦国民健康保険料の減免
◦国民年金保険料の減免
◦高額療養費
◦生活福祉資金(貸付)
◦就学援助
◦奨学金
◦生命保険の「高度障害状態」と住宅ローンの返済
家族の支援等
本人だけでなく、介護をする家族を支援する制度等についても、相談を受ける支援者は、情報収集しておく必要があります。有効に利用できれば、暮らしの応援につながります。
【詳細はこちら】
◦家族の会
◦介護休業制度

自立や尊厳を守る支援等
判断能力が低下してきても、症状に応じて自立や尊厳を守るための制度等があります。
【詳細はこちら】
◦地域福祉権利擁護事業
◦成年後見制度